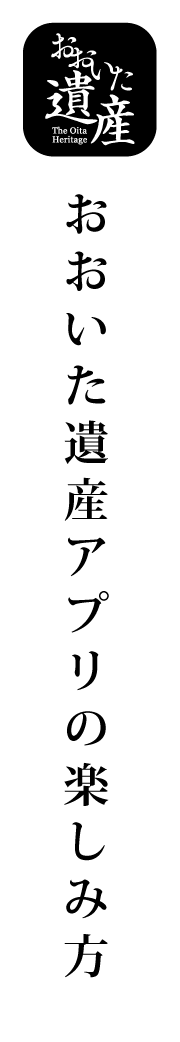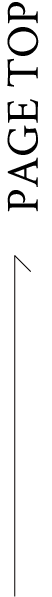国東半島にはため池が多い。中央の両子山(721メートル)から海岸へ。中には、山の斜面に沿ってため池が縦に並んでいるところもある。それぞれを水路でつなぎ、下流のため池の水が不足すると、上流から水を落とす。
農業には水が欠かせない。傘を伏せたような半島の地形は険しく、川は急こう配。海岸までの距離は短く、雨水は流域を十分に潤す間もなく海に流れ込む。田畑に使える水は、ほかの地域に比べて十分とは言えない。多雨、少雨の年があるにしても、雨を貯水するため池がなくては、稲作はおぼつかない。ため池は、自然に向き合い、農業で暮らしてきた人々の知恵と努力の結晶だ。
ため池の周りにはクヌギ林が広がる。本州以南の里山でよく見かける落葉高木で、たきぎや炭として使われてきた。つい半世紀前までは暮らしに欠かせないエネルギー源だった。
クヌギは伐採し、シイタケを栽培する榾木に使う。成長は早く、伐採後、15年もすれば元のように大きくなる。伐採と育林を繰り返し、クヌギを絶やさないように利用する。自然のリズムに合わせたシイタケ栽培である。
ため池とクヌギ林、それを利用した農林業が「世界農業遺産」に結びついた。「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」である。対象は国東半島と宇佐市一帯の4市1町1村・1323.75平方キロ。古くから、宇佐神宮と六郷満山の仏教文化を支えてきた地域だ。
世界農業遺産は「国連食糧農業機関」が伝統的な農業と生物が豊かな環境、農村の文化や景観を維持・保全している地域を選定しているものだ。国内では「トキと共生する佐渡の里山」「阿蘇の草原の維持と持続的農業」などがある。
国東半島・宇佐の世界農業遺産は「循環」が大きな意味を持っている。循環にはクヌギ林、つまり里山が深くかかわっている。クヌギの林はしっかりと根を張り、土壌の保水力を高め、ため池の水へとつながる。やがては田畑を潤し、海へと流れ、土壌に含まれる大地の栄養分を含んだ水が海を豊かにする。
大きく眺めれば、クヌギ林とため池、それを利用する稲作やシイタケ栽培を通して、鎖がつながるように緑と水と土がつながっている。人々がつくりあげてきた持続する農林水産業の姿である。