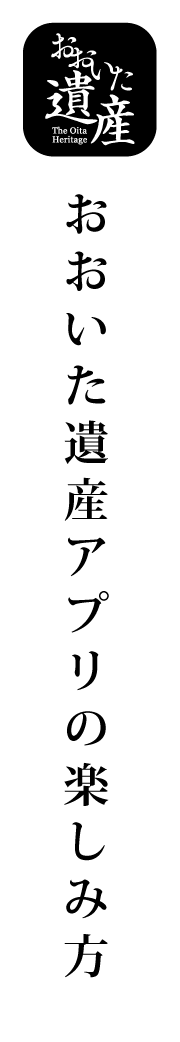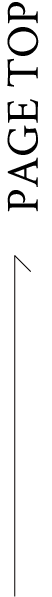中津市北原の原田神社では毎年2月初め、万年願の行事で人形浄瑠璃が演じられる。また、同市伊藤田の古要神社では旧暦閏年の10月例祭で傀儡子の舞として古要舞と神相撲が奉納され、国の重要無形民俗文化財に指定されている。
北原人形芝居には、鎌倉幕府の執権・北条時頼にからむ創始伝説がある。時頼が諸国巡視で北原に来た際、病に伏し、村人の看病で回復した。その全快祝いで村人が踊りや人形芝居を見せたところ、時頼は「踊りを業として世を渡れ」とことのほか喜んだとか。
北原芝居の特色は、一般的な人形の扱い方である「三人遣い」のほか、一人で操る「はさみ遣い」が伝わること。全国的にも極めて珍しい。
万年願では保存会の人たちによる「大功記」や「伊達娘恋の緋鹿子」などのほか、地元の三保小学校の児童による「傾城阿波の鳴門」もあり、当日の境内は大にぎわい。
古要の傀儡子も伝承は古い。奈良時代に南九州で隼人の乱が起きた時、宇佐神宮も加わって鎮圧に派遣され、戦場で傀儡子を操り隼人が見とれているのを狙って攻めた。以来、隼人の霊を慰めるため舞わせたという。
傀儡子は両手と片足だけが動くたいへん素朴なもの。舞には26体、相撲には東西各12体が登場する。相撲は東西対抗戦で最初は交互に勝つが、途中から東軍の連勝となり、最後には西軍の住吉神が総がかりの東軍を圧倒する。
傀儡子のつくりはかわいらしく、動きも単純でユーモラスだが、何となく厳粛。なにしろ傀儡子そのものが神なのだ。
北原も古要も宇佐神宮や薦八幡社にゆかりの深い村で、神社に奉仕する人の中から芸能、あるいは運輸に携わる人たちが出たらしい。これを散所と呼んだ。江戸期まで各地にあり、豊後高田市の算所芝居や杵築市の歌舞伎なども有名である。